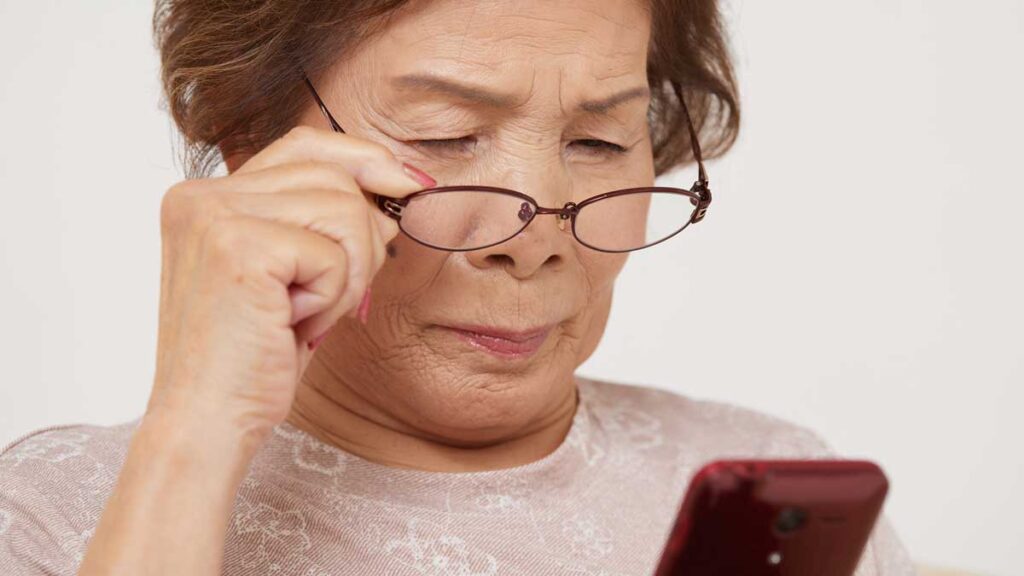
60歳以上におすすめの資産運用の使い分け方
預貯金と投資のバランスを取る
60歳以上にとって最も大切なのは「生活資金の安心感」です。年金を中心にした収入に加え、手元にいつでも引き出せる預貯金を確保しておくことが基本になります。そのうえで余裕資金があれば、リスクを限定した範囲で投資を組み合わせると、インフレ対策や資産の目減り防止に役立ちます。
個人向け国債や定期預金の活用
投資に不安を感じる場合、個人向け国債(特に変動金利型10年)や定期預金は有効な選択肢です。元本が保証され、利息も得られるため「減らさない資産運用」として安心感があります。大きなリターンは期待できませんが、安定した資産保全を重視するシニア世代に適しています。
→シニアにおすすめの「個人向け国債」「定期預金の活用」の解説はこちら
投資信託を小さく利用する
一方で、余裕資金の一部を投資信託に振り分けることは有効です。
- 値動きの小さいバランス型投信
- 国内外の株式と債券に分散投資するインデックス型投信
こうした商品を選べば、比較的安定しつつインフレに対応できます。NISAを利用する場合も、生活資金に手を付けず「一部だけ運用する」というスタンスが重要です。
→低リスクで始める「投資信託」の解説はこちら
保険の見直し
保険は資産を増やす商品ではなく、医療・介護などの突発費用を保険料に置き換える“リスク移転”の道具です。公的制度と手元資金で足りない部分だけを補うことで、固定費を抑えつつ安心を確保できます。過去の契約の重複や過剰な特約は整理し、必要期間・必要額に絞るのが60代には有効です。
不動産収入の活用
老後の家計に毎月の現金収入を足す方法です(ここでは賃貸用不動産の運用を指します)。大きな値上がりは期待しづらい一方、入居が続けば手取りが安定し、年金や預貯金と合わせて生活費の下支えになります。空室や修繕、金利上昇などのリスクがあるため、60歳以降は借入を抑え、生活費の一部を賄える“無理のない規模”での運用が基本です。
自分のライフプランに合わせる
- 旅行や趣味に資金を使いたい人
- 子や孫への支援を優先する人
- 医療や介護の備えを重視する人
目的によって最適な資産配分は変わります。NISAは万能ではありませんが、正しく理解して「使う」「使わない」を判断すれば、老後の暮らしを安定させる有効な手段の一つとなり得ます。




