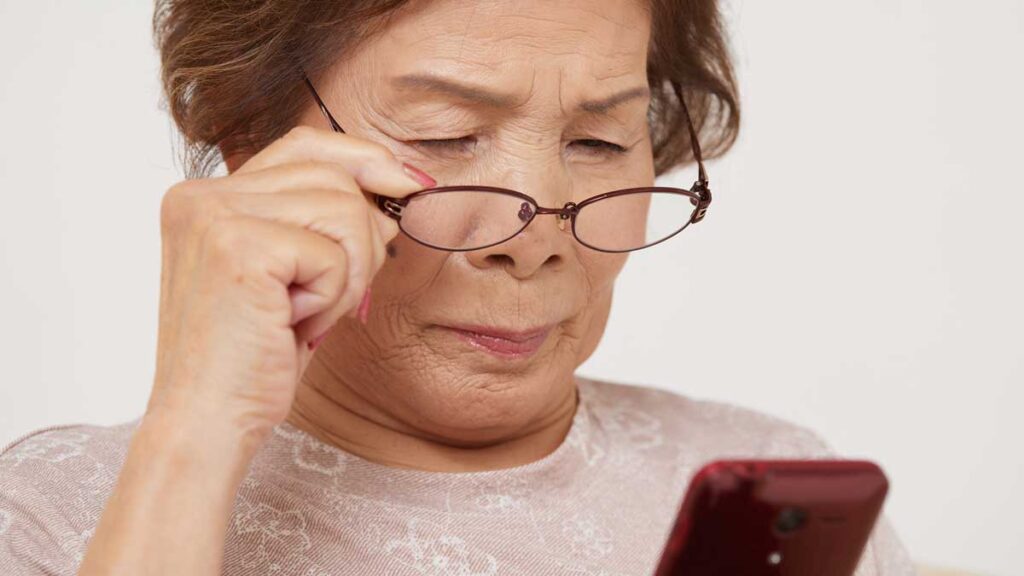
注意点1:運用期間の制約がある
NISAの基本は「長期投資」
NISAは「長期・積立・分散」を基本理念とした制度です。新制度では非課税期間が無期限化されましたが、実際には「長期間にわたって資金を寝かせられるかどうか」が大きなポイントになります。投資成果の多くは「時間」によって生み出される複利効果によるものです。長期で運用を続けるほどリターンが安定しやすい一方、短期間で解約すると元本割れのリスクを抱えたまま終える可能性があります。
60歳以上にとっての20年
例えば、60歳からNISAを利用し始めると、80歳までの20年間を運用期間として想定することになります。健康で資金に余裕があり、20年間手を付けずに運用できれば理論上は若い世代と同じ非課税メリットを享受できます。
しかし現実には、定年後のライフプランや体調の変化により、20年間投資を継続できないケースが少なくありません。
- 住宅の修繕
- 医療費や介護費の増加
- 子や孫への資金援助
こうした出費が生じると、想定より早く資金を引き出す必要が出てきます。その際、投資がプラスに転じる前に解約すれば「元本割れ」のまま終わってしまうリスクがあります。
複利効果が活かしづらい
- 30代で20年間運用 → 資産はおおよそ1.3倍に
- 60代で10年間運用 → 資産はわずか1.1倍にとどまる可能性
同じ利回りでも、残された時間が短ければ伸び幅は小さくなります。つまり「若い人には強力な武器」でも「高齢者には効果が限定的」となるのです。
取り崩し時期とのズレ
もうひとつの問題は「資産を取り崩す時期」と「投資の成果が出る時期」が一致しないことです。老後の生活資金を確保するには、70代前半から定期的に資金を使い始める人が多いですが、投資成果が安定して現れるのは10年以上先。ここにズレが生じると、必要な時に十分な資金を得られないリスクが高まります。
このように、60歳以上がNISAを利用する際には「時間」という制約が大きくのしかかります。しかし、問題はそれだけではありません。老後の暮らしに欠かせない「自由に資金を使える安心感」にも、NISAは影響を与えるのです。
次のページでは、この流動性の問題をわかりやすく解説します。




