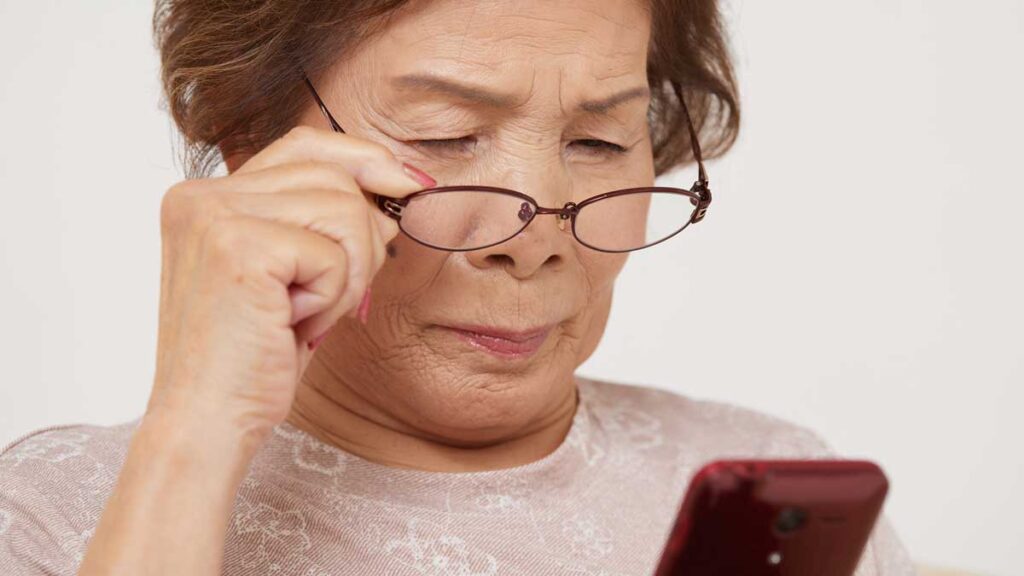
新しいNISA制度が始まり、幅広い世代に投資ブームが広がっています。新聞やテレビでも「NISAで資産形成を」といったフレーズが繰り返され、年齢を問わず口座開設が増えているのが現状です。
ですが、「誰にとってもNISAは得」というわけではありません。特に60歳以上の方の場合、NISAの仕組みがライフステージや資金計画と噛み合わないケースも少なくありません。ここでは、60代以降が注意すべき3つの視点を整理していきます。
資金拘束リスクに要注意
投資は「余剰資金」が前提
NISAの最大のメリットは「投資で得た利益が非課税になる」という点です。しかしその効果を十分に享受するには、数年単位での保有が前提となります。
突発的な支出に対応できない可能性
ところが60代以降では、突発的な医療費や介護費、子どもや孫への援助など、予想外の出費が増える場面も多くなります。もし必要になって投資を解約する場合、相場が下がっているタイミングなら損失が確定してしまう恐れがあります。
「必要になるかもしれない資金は投資に回さない」という鉄則は、若い世代以上にシニア世代にとって重要です。
利益よりも生活安定が優先される年代
年金+貯蓄が生活の基盤
60歳以上では、生活の柱は年金やこれまでの貯蓄です。そのため重視すべきは「大きな利益を得ること」ではなく「安定して暮らせること」です。
相場変動は心理的負担に
株価の変動で資産が増減すると、精神的な不安が大きくなる人もいます。若い世代なら「長期で保有すれば回復する」と考えられますが、シニア世代にとっては「待つ時間」が限られているのが現実です。
そのため、NISAを使ってリスク資産を増やすよりも、現金や安全性の高い金融商品を中心にした方が安心できる場合は少なくありません。
NISAの節税効果は限定的
非課税メリットは利益が出てこそ
NISAは投資で得た利益が非課税になる制度ですが、そもそも利益が出なければ恩恵はありません。株価が下がれば非課税どころか元本割れでマイナスです。
高齢世帯では効果が薄いケースも
さらに高齢世帯は、年金中心で所得税率が低い場合が多くあります。この場合、課税額自体が小さいため、非課税のメリットは若い世代ほど大きくありません。結果として「節税目的でNISAを使う」意義は限定的といえます。
選択肢の再考を
NISAは便利な制度ですが、すべての人に最適とは限りません。特に60歳以上の方は、まずは生活費や医療費など「必ず必要になる資金」を現金で確保することが優先されます。
そのうえで「余剰資金をどう動かすか」を考えるのが現実的です。資産を大きく増やすよりも「減らさない・安心して使える」ことを目的にした方が生活の安定につながります。
シニア世代にとっては、あえてNISAを利用しないという判断も十分に合理的なのです。




