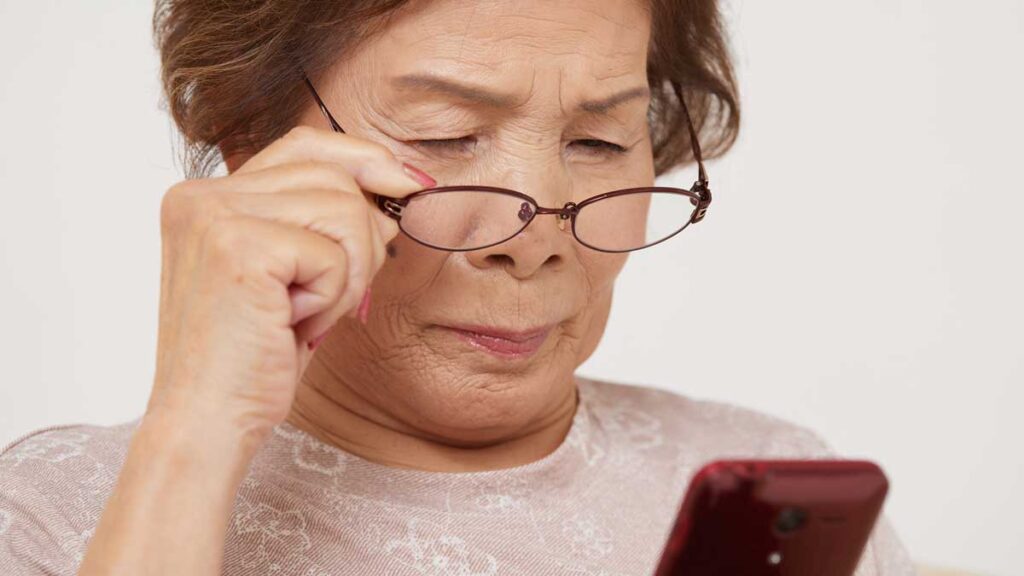
60歳以上の人はNISAをすべきでない理由
利用者数が増えている「つみたてNISA」
投資にはリスクが伴うことで、避けている人もいるのではないでしょうか。
「60歳以上の人がNISAをすべきでない」と言われることには、理由があります。
ですが、正しい知識をもって適切な活用ができれば、老後資金の助けになる可能性も十分にあります。
シニア世代がNISAで利益を得るためには、いったい何に気を付けるとよいのでしょうか?
つみたてNISAってどんな制度?
新制度の概要
2024年からNISA制度は大きく改正され、より幅広い世代が利用しやすい仕組みに生まれ変わりました。従来は「一般NISA」と「つみたてNISA」に分かれていましたが、新制度では非課税枠が一本化され、年間最大360万円まで投資できるようになっています。
投資枠は「つみたて投資枠」と「成長投資枠」に分けられ、以下のように目的に応じた活用がしやすくなりました。
- つみたて投資枠:長期・積立・分散投資を重視した投資信託など
- 成長投資枠:株式やETFなど幅広い商品に投資可能
さらに、非課税期間は無期限化され、売却のタイミングを気にせず長期投資を続けられる仕組みに改善されています。
利用者層の変化
一見すると魅力的な制度ですが、実際の利用状況をみると世代間で差があります。2014年の制度開始当初、口座開設者の半数以上は60歳以上でした。リタイア後の資金活用先として注目された結果です。
しかし2024年12月末の統計では、40代以下の割合が拡大し、依然として60歳以上も32.1%を占めているものの、相対的な比率は低下しました。この変化は、制度の設計が「どの世代に有利に働くか」を示しています。
若い世代が有利な理由
NISAの設計思想は「長期投資」にあります。非課税期間が無期限化されたとはいえ、複利効果を得るには10年、20年という時間が必要です。
30代で始めた場合
年間40万円を投資し、平均利回り3%で20年間運用すると、元本800万円は約1,080万円に増えます。
60代で始めた場合
同じ条件で投資しても、80歳まで20年間フルに継続できる人は限られます。生活上の理由から途中で取り崩す可能性も高く、結果として複利の恩恵を受けにくいのです。
シニア世代の最適解でない理由
60歳以上の人は「資産を増やす」よりも「資産を減らさない」ことを優先する傾向があります。そのため、成長性を追うNISAの特性とは必ずしも一致しません。制度自体は非常に有利である一方、シニア世代にとっては「必ずしも最適解ではない」ことが、利用者数の推移にも表れています。
NISAは誰にとっても万能ではなく、年齢や生活状況によって適切な使い方が異なります。特に60歳以上が利用する場合には気を付けるべきことがあります。
次のページから、3つの注意点について詳しく見ていきます。




